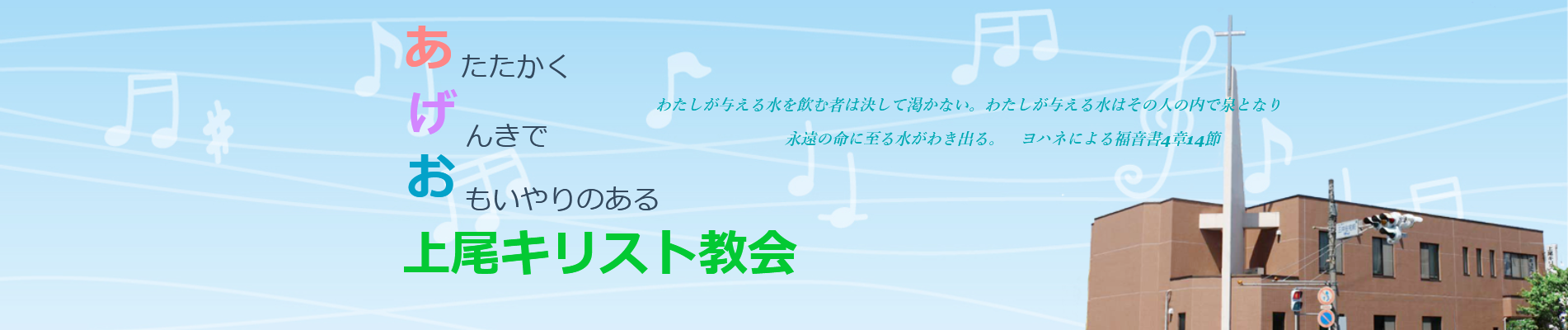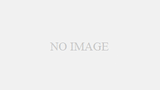「対話」の必要性が叫ばれながら、豊かな対話に至らないという声を聞くことがある。日常生活におけるコミュニケーションとして話をしたり、雰囲気を和らげるために「会話」はする。また、相手を説得し、論破するために「議論」はする。しかし、互いに理解を深め、信頼関係を築くために「対話」することは不慣れである。
それは私たち日本人は同調性を好み、「以心伝心」や「阿吽の呼吸」のように積極的に言葉を交わさなくても理解することを美徳とする習性があるからではないか。
しかし、今日の多様化する社会の中で、自分と立場や考え方や文化の違う人たちと共に生きるためには、「対話」による相互理解が不可欠になる。「対話」は、お互いの意見を尊重しながら話し合うため、自分の考えを絶対化することなく、相手の意見を率直に受け取ることが重要になる。「話すこと」よりも「聴くこと」が重視され、ただ「聴く」だけではなく、相手の話を「聴くことで感じとる」ことが求められる。対話を重ねることで、相手を理解し、どのように対処すべきか示されていく。
聖書は「対話」の書である。ヨハネ4章では、主はサマリアの女性とヤコブの井戸の傍らで対話をしながら、彼女の求めに応えて救いの道を示し、まことの礼拝へ導き、主を証しする者へと変えてくださった。サマリアの女性からするならば、交際することのなかったユダヤ人の主が、自分と対話することなど考えられなかったので、驚きであった。しかし、主は「わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」ヨハネ4:14と、すべての人を分け隔てなく招くのである。
聖書は、個人に宛てた書ではなく、「イスラエルの民」と「教会」に宛てた書なので、独りで読んでいてもわからない。教会で一緒に御言葉を聴き、一緒に御言葉を学び合うことによって、神の御心が何であるのか、その御心を実現するためにどのように生きたらよいのか、示されていく。毎週、礼拝で説教を聴くだけではなく、礼拝前に行われる「分級」に出席して、御言葉を一緒に学び合うことによって、主を深く知り、他者の思いを知り、祈りへと導かれていく。それは、週の半ばにもたれる「祈祷会」も同じで、御言葉を一緒に学び合い、一緒に祈り合うことによって、神理解と相互理解が深まっていく。Zoomで家庭からでも祈祷会に出席することができる。神との対話を豊かなものにしていくために、「分級」や「祈祷会」はとても大切であるので、その時間を捧げていきたいものである。