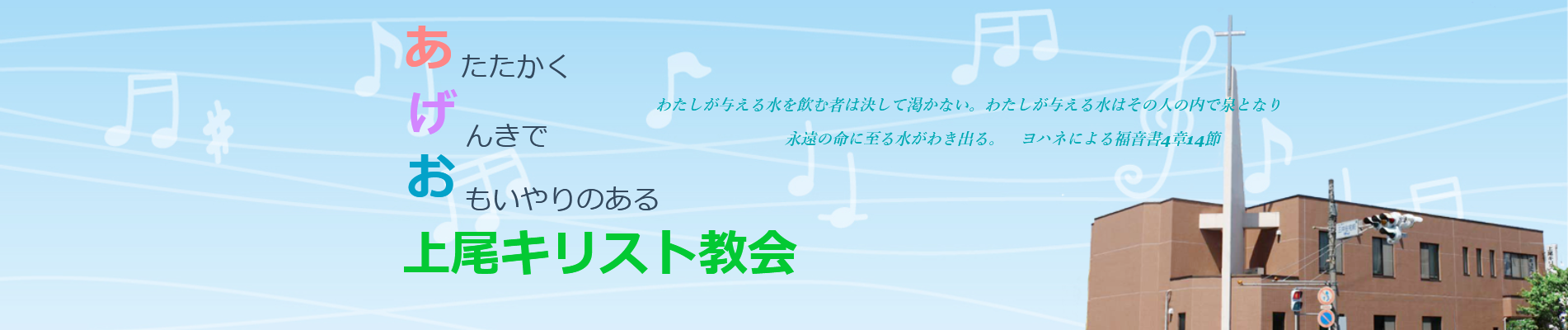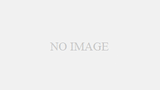上尾教会は、2年間にわたり「一人ひとりを喜び、共に生きる教会」という主題を掲げて歩んできた。「共に生きる教会」とは、誰と「共に生きる教会」なのだろうか。キリスト教会が「共に生きる」という場合、教会の歩みへの深い反省に基づく必要があると思う。教会は、長い歩みの中で多くの過ちを犯してきた。振り返れば、教会が戦争に加担し、弱者を圧迫し、差別を助長し、不正を見逃してきた惨憺たる歴史がある。
被差別部落出身者、障がい者、ハンセン病患者、路上生活者(ホームレス)、在日外国人、LGBT(性的少数者)などに対して、差別や偏見から、教会は礼拝や交わりから締め出してきた。私が30年前、連盟の「障がい者と教会委員会」の設立にかかわった頃、全国の教会にアンケートを出したところ、中には「幸いにも、まだ教会に障がい者はおらず、バリアフリートイレもスロープも必要はありません」といった回答があった。障がい者は不幸だという認識があり、主に救いを求めてきた人々を締め出してきた。
そこには、「異質」のものより「同質」のものを好む傾向がある。出自が似かより、健康で社会的に円満な人は同質だと思い込み、異質なものは「よそ者」と見なし、排除してきた。そして日本社会に見られる「同調圧力」を教会にも持ち込み、多様性を認めず、一人ひとりをありのまま受け入れることを疎かにしてきた。このような枠組みに捉われている限り、教会は「排除の論理」にいつまでも縛られることになる。
ファリサイ派の人々がまさにそうであった。「あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。」申命記6:5という掟は、彼らにとっては「律法を守る」ことを意味した。 しかし、「律法を大切にし、神を大切にする」ことを重視するあまり、目の前にいる人々・・律法を守ることのできない人、罪を犯した人、重い病を患った人、障がいのある人、異邦人などが見えなくなり、排除していった。だから、主は彼らに、「隣人を自分のように愛しなさい。」マタイ22:39、「他者を自分のように大切にすることが、神を大切にすることである」と言われて、誰とでも友となられた。
この歴史の反省に立って、教会の宣教姿勢も大きく変ってきた。これまでは、人々を教会に誘ってバプテスマを授けることが宣教だったが、教会が苦しんでいる人々の所へ出て行き、その人たちのために何かできることをすること、それ自体を宣教と考えるようになった。「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」マタイ25:40、この主の言葉を実践する教会でありたい。4