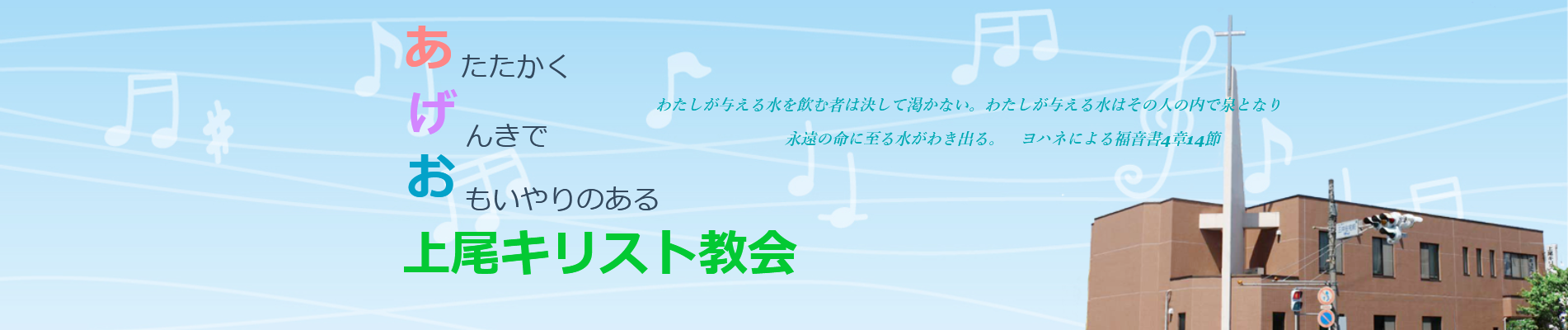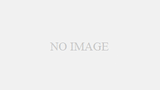上尾教会は、2年間にわたり「一人ひとりを喜び、共に生きる教会」という主題を掲げて歩んできた。そこには、「神の目から見て、一人ひとりが、価高く、貴い存在である。」イザヤ43:4(私訳)が根底にある。私たち一人ひとりに、等しく、神からの尊厳が与えられている。尊厳とは、かけがえのない存在ということである。私たち一人ひとりは、かけがえのない存在として神に創られた、大切な存在なのである。
しかし、教会の歩みを振り返る時、「一人ひとりを喜ぶ」ことをしてきただろうか。かつて全国少年少女大会の時に献身の招きがあったが、女性に対しては「牧師夫人」としての献身者を募った。女性は牧師になりたくてもなることは許されず、神学校に入ることもできず、牧師の配偶者になって献身するしかなかった。そして、やっと女性も牧師になることができる時代を迎えたが、男性牧師(それも妻子のいる)が優先的に教会に招聘され、女性牧師が招聘されるのは最後になる場合が多い。又、殆どが小規模教会への招聘である。教会の歩みは、性差別が長く続いてきている。
これは、女性牧師だけのことではない。もてなしをするマルタ的な女性が好まれ、食事を担当する性別役割分担がなされてきた。そして年頃になると、「彼氏はいないの」「結婚はまだ」「子どもは‥」といったセクハラ発言を受け、辛い思いをしてきた。又、自分の意見が通らないと声を張り上げ、パワハラ発言をして、人に不快な思いをさせてきた。教会は、ハラスメントの認識が薄く、人権を無視してきた。
人権とは、「人間が、人間らしく生きてゆく権利」である。世界人権宣言の第一条には、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」と掲げている。この第一条を詩人の谷川俊太郎さんは、「わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。」と訳している。「一人ひとりを喜ぶ」人権感覚を身につけていくためには、絶えず学んで、自分を変えていくことである。主は「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。」マタイ9:17と言われた。長く生きるほど、自分の生き方を変えることは難しい。しかし、差別やハラスメントに無頓着な古き自分を変えていかなければ、主の福音に生きる喜びを証することはできない。自分を変えてこそ、「一人ひとりを喜ぶ」ことができる。